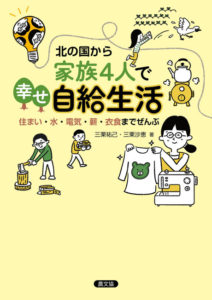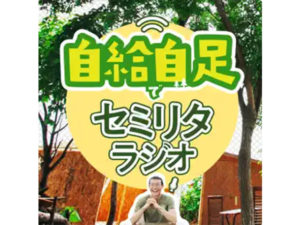北海道・三栗祐己
北海道の山の中で、住まいや電気(太陽光発電)、水道などを自分たちでつくりながら、働きすぎず、穏やかに、豊かに暮らしている三栗さん一家のお話です。
2023年6月にスタートした本連載は今回が最終回です。三栗さん、どうもありがとうございました。

第1話でもお伝えしましたが、わが家はタイの山奥のパーマカルチャー・ファームに5年間、トータル300日以上滞在しました。この旅は、用意されたパッケージツアーではなく、自分で旅程を組み立てて全てを自分で決める旅でしたので、色々なトラブルとともに、多くの学びと経験を得ることができました。
今回は、その旅から得た「生き抜く力」について、お話しいたします。
旅で身についた3つの「生き抜く力」
僕が旅で身についたと感じた、3つの「生き抜く力」を紹介します。
①ピンチに対応する力
海外の旅では、トラブルがない方が珍しいくらいに、頻繁にトラブルが発生します。
例えば、あるとき、次の目的地に行くためにバスを待っていましたが、数時間経ってもバスが来ません。こんなときはまわりの人に聞きたいのですが、田舎町のため、タイ語しか通じません。普段、見知らぬ人に話しかけるのは苦手な僕でしたが、さすがに子どもを連れて野宿するわけにもいかず、勇気を出して現地の人に話しかけました。
身振り手振りを交えながら、何とかコミュニケーションをとってわかったことは、「その日はバスが来ない日で、移動するならヒッチハイクしかない」ということでした。ヒッチハイクも苦手なので、できればやりたくありませんが、このまま日没を迎えれば、子連れでの野宿が確定します。必死の思いでヒッチハイクし、何とか目的地に到着、無事にホテルにたどり着きました。
②今ある幸せを感じられる力
僕たち一家が滞在したところは、電気・ガス・水道など、公共のライフラインがありません。水道は、山の湧き水を、2km先から自分たちで配管して引っ張ってきたものです。乾季で水源の水が涸れる、配管がネズミにかじられて破損するなど、断水に見舞われるたびに山に入って対応しました。



ガスもないので、火を使うには、普段から薪を拾い集めて、ストックしておかなくてはいけません。

電気も太陽光発電なので、照明など必要最低限をまかなうという生活でした。
しかし、ライフラインが充実しているはずの日本では、なぜか、普通に暮らしていても様々な不安がつきまといます。こうした経験をして帰国すると、電気・ガス・水道が整った日本の当たり前の暮らしがいかにありがたいものであるかを実感しました。普通に生きているだけで幸せを感じられるようになり、以前抱えていた様々な不安も少なくなりました。

③「他人軸」でなく、「自分軸」で考える力
日本では、何かが起きると、「みんなはどうするかな」「普通はどうするだろう」「こうするのが常識的だよね」といった判断で行動を決めることが多いと思います。これは、「他人軸」で判断をするということであり、どうしても受け身になってしまいます。しかし海外では、「What’s your idea? (あなたはどう思うの?)」と意見を求められることが多く、ときには激しい議論も起こります。こうした環境にいると、「自分は本当はどうしたいのか」と、「自分軸」で考える習慣がつきます。そうして日本に戻ってくると、まわりの意見やインターネットの情報に振り回されることなく、自らの意思で適切な判断をして行動することができるようになったと感じます。
妻の学び
妻の沙恵です。家族で旅をして感じたことをシェアさせていただきます。

①家族で助け合うこと
家族で旅をすること。家族で一緒に初めてのことに挑戦しました。
バンコクから丸一日、バスに揺られていくつもの山を越えていく旅です。英語すら通じなくなっていく不安。メールでのやり取りだけで目的地を目指します。大人の不安も丸見えのなか、子ども達はついてきます。家族で団結して困難を一つずつ越えていくという経験でした。
でも、本当に助け合うことが必要な場面では、どんなに小さくても立派に家族の中での役割をこなしてくれます。お互いの心の揺れを感じ、それに寄り添いながらそれぞれができることを見つけていくんだと目の当たりにした瞬間が沢山ありました。そうして少しずつ目的地へ。
目的地に到着した途端、子ども達にも心からの感謝が溢れます。「ありがとう」という言葉が家族の中に沢山飛び交うようになったのも、こんな時間の積み重ね。旅は頑張った成果をすぐに見せてくれます。
覚悟と決断と、行動でしか前に進めないけれど、そうしてたどり着いた目的地で安堵しながら、自分自身を讃え、家族一人一人を讃えます。そして、私のこれからの人生は「きっと、大丈夫」、我が子を見て「あなたも、大丈夫」、と自分自身や家族に対する信頼感が深まっていきます。

家族は一番小さな集団。小さな小さな村。何かが起きても、家族全員が不安になることは意外に少なく、希望を見出せた人が落ち込んだ人を救い出してくれます。
家族で困難を乗り越えてみて、大人とか子どもとか関係なく、人は誰かに支えてもらいながら生きているんだと知ることができます。
そうすると時折おとずれる困難なことでも、そこを超えるまで頑張ることができます。 大事な力をこの旅でつけてきたなと思っています。
②子どもに「寄り添う」「信じる」こと
それを何度も静かに観察してきた今は、こんなときこの子はどうするだろうと考え、信じることができます。子どもを信じることは、大人の側が先回りして手出しをすることなく、ただ観察し、その子がどういう人間かを知っていくことでつく力だと私は思います。
家族で共に過ごした旅の時間は、ぶつかり、笑い、困難を超える作業が度々ありました。でも、この世に生まれ出て1番初めの集団である家族を、まずは大事にできることから、優しさは広がっていくと思います。子どもが小さいうちに、そこに時間をかけられてよかったと今は思っています。
我が家はそろそろ子ども達の巣立ちを迎えようとしています。家族という小さな集団で培った優しさや知恵を、社会という大きな世界で使っていくとき。あっという間の10数年でしたが、思う存分一緒に過ごし、子ども達のやさしさにも触れてきたので、「あなたなら大丈夫!」と、僅かな心配はそっとしまって送り出せそうです。
さあ、もう少し、一つ屋根の下にいられる時間を楽しもう。

村の子ども達の「生き抜く力」への憧れ

タイにいるとき、息子がカニ取りに挑戦しました。
乾季の沼で楽しそうにカニ取りをしていた村の子達と一緒に遊んだけれど、自分だけ怖くて手を入れることができなかったのが悔しかったそうです。村の子達が木登りをして果物を取ったり、魚を取る、そんなしなやかさがかっこいいと思ったそうです。
恐る恐る、でも覚悟を決めてカニの穴に手を入れて探し、捕まえた時の感動。2、3回挑戦したら、そのまま楽しさが勝り、ファームのみんなに振る舞えるだけ集めました。今度はそれを調理。 村の子達をしっかりみていたようで、スーッと流れるように下処理を済ませ、火おこしをして調理を終えました。


生きる力を持った人たちに対する憧れは、人としての本能なのでしょうか。息子は今でも忘れないとても大きな経験をしました。そしてそんな息子から私たちも、生きる力や日々の安心感について考えるきっかけをもらいました。
*
以上、家族で行った海外長期滞在から得た「生き抜く力」という学びを紹介させていただきました。
数々のトラブルとともに得た海外での経験は、現在の山暮らしという挑戦に、大きく役立っています。長期滞在でなくとも、イチから自分で手配する海外への旅では、決断力・行動力が身につきます。そしてそれは、今後豊かに生きていくための「生き抜く力」になると考えています。機会がありましたら、挑戦してみるとおもしろいですよ。
1年半にわたる連載をお読みいただき、ありがとうございました!
今後も家族で、農的暮らしの魅力や、具体的なやり方などを発信していきます。
パーマカルチャー研究所の三栗一家を、引き続き、よろしくお願いいたします。
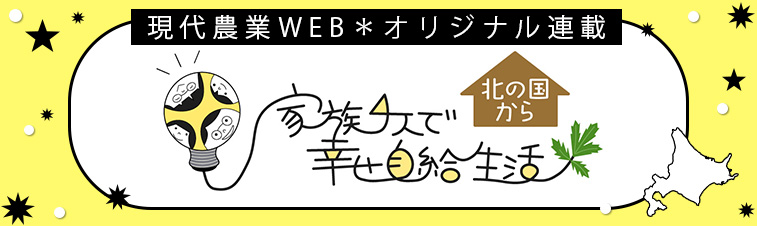
- 第1話(6月12日) 私のパーマカルチャー
- 第2話(6月26日) 極寒のマイホーム
- 第3話(7月10日) 雨漏りとペンキ塗り
- 第4話(7月24日) トイレを手作りする
- 第5話(8月21日) お風呂を手作りする
- 第6話(8月28日) 断熱のお話
- 第7話(9月18日) 我が家の電力自給
- 第8話(9月27日) 北海道大停電 頼りは太陽光発電と人のぬくもり
- 第9話(10月13日) 水を自給する
- 第10話(10月25日) 暖房を自給する(前編)
- 第11話(11月9日) 暖房を自給する(後編)
- 第12話(11月28日) スーパーで野菜を買わない実験
- 第13話(12月15日) みんなで畑づくり 柵の設置、定植
- 第14話(1月5日) ニワトリ小屋づくり(前編)
- 第15話(1月22日) ニワトリ小屋づくり(後編)
- 第16話(2月20日) 食の自給① 梅干し&納豆
- 第17話(2月29日) 食の自給② 麹、味噌、醤油
- 第18話(3月15日) 食の自給③ 冬を乗り切るための漬け物づくり
- 第19話(4月9日) 食の自給④ 薪ストーブを使ってつくる干し野菜&おやつ
- 第20話(5月16日) 服作り(前編)
- 第21話(6月24日) 服作り(後編)
- 第22話(9月13日) 石けん作り
- 第23話(10月21日) 暮らしから学ぶ
- 第24話(12月17日・最終回):旅から学ぶ
本連載が、単行本になりました!

北海道札幌市の山奥で「パーマカルチャー研究所」を運営。パーマカルチャーとは、持続可能な暮らしのこと。家族4人で自給自足の暮らしをしながら、その暮らしから得られたパーマカルチャー的価値観を伝えることを仕事としている。著書『北の国から 家族4人で幸せ自給生活』(農文協)が発売中。
(写真提供:金本綾子)
住まい・水・電気・薪・衣食までぜんぶ
三栗祐己・三栗沙恵 著
衣食住の生活技術や水・エネルギーの自給で、豊かで楽しい暮らし。プレハブの住まい、オフグリッド太陽光発電、薪ストーブ、野菜の貯蔵や保存食作り、衣類や石けんの手作りなど、「自給生活」を楽しむコツを大公開。