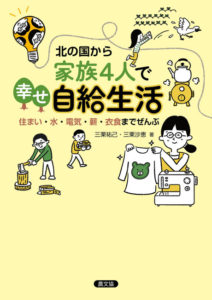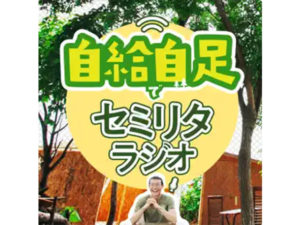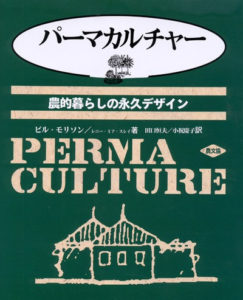北海道・三栗祐己
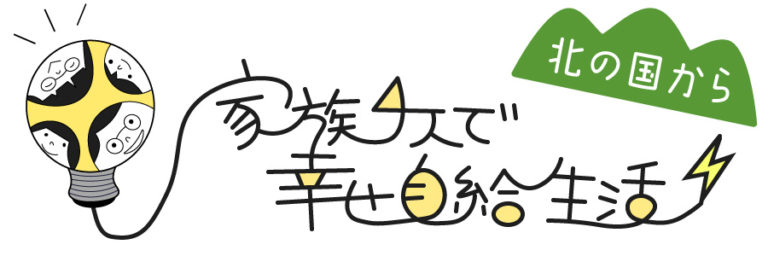
月刊『現代農業』の読者のみなさん、お久しぶりです。現代農業WEBでは、はじめまして! 私は、北海道札幌市の山奥で自給自足生活をしている三栗祐己(44歳)です。現代農業で2021年4月号〜2022年4月号までの1年間、全10回の連載で僕たち家族4人の暮らしを紹介させていただきました。このたび縁あって、web版限定で連載を再開することになりました。月に2回、誌面に載せきれなかったことなどを含めて、新たに書いていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。
では、初回は改めて自己紹介から――。
東京電力を辞めてタイのジャングルへ

今から約20年前、僕は大学の工学部で太陽光などの自然エネルギーを活用する、新しい電力システムを考える研究室で学んでいました。世界のエネルギー問題を、自分の研究で解決できるような仕事に就きたいと思うようになり、卒業後は(株)東京電力に入社しました。
入社7年目には希望の研究所勤務となり、順風満帆な日々を過ごしていましたが、2011年3月11日、東日本大震災が発生。原発事故によって、エネルギー問題を解決するどころか、かえって悪化させてしまったことに大きな絶望感と無力感を抱きました。
東京電力を辞め、函館高専に電気の教員として採用されたものの、慣れない仕事と、当時5歳の息子と1歳の娘の育児を両立できずに退職。次の仕事を考えていた頃に思い出したのが、タイのジャングルでの暮らしです。
タイに訪れたのは2013年。ちょうどまとまった連休が取れることになり、家族で海外旅行の行き先を検討していたところ、妻が子育て雑誌である記事を見つけました。タイの山奥のジャングルで日本人が子育てしているという内容で、なんとなく面白そうだから行ってみようか。そんな軽い気持ちで、タイの「パーマカルチャー・ファーム」を訪れることにしました。
山奥にあるそのファームには、電気やガス、水道といったライフラインがありません。ガスの代わりに山の豊富な木を薪として使い、水道の代わりに井戸や山の湧き水を利用。小さな照明やケータイの充電には、たった数枚の太陽光パネルを使っていました。
エネルギーや水が、すべて自分たちの手の届く範囲、目に見える範囲で賄われている。その安心感は、これまで大規模なライフラインに依存して生きてきた僕にとっては、とても新鮮な感覚でした。

「パーマカルチャー」という言葉を知ったのもその時です。『パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン』(農文協)によると、パーマネント(永久の)とアグリカルチャー(農業)をくっつけた言葉で、同時にパーマネントとカルチャー(文化)の短縮形でもあるそうです。僕はよりシンプルにわかりやすく、「持続可能な暮らし」と解釈しています。
自然の中で住まいや畑、電気や水道など、暮らしに必要なものをすべて自分たちで作りながら、働きすぎることなく、穏やかに豊かに暮らすライフスタイル。僕もそんな暮らしを自分でつくっていきたいと考え、教員を辞めた後に新たな勤め先は探さず、2015年に「パーマカルチャー研究所」を立ち上げました。
北海道の山奥で自給自足生活をスタート
とはいえ、当時住んでいたのは住宅街にある普通のアパート。そこで原生林の土地を購入し、住まいやライフラインをイチから手作りすることにしました。まず太陽光パネルを設置して、その電気で電動工具を動かし、小さな小屋やコンポストトイレなどを作りました。


そんな日々の活動の様子をブログで毎日発信していたところ、札幌市内で自給自足の山暮らしを20年以上続けている70代のご夫婦に出会いました。野菜などの食べ物はもちろん、住まいや薪ストーブ、太陽光発電など、暮らしに必要なあらゆるものを手作りしていて、タイで見てきたような、いや、それ以上の自給自足生活を実現していました。
感動してご夫婦の元へ何度も通いつめていたところ、土地もプレハブ(住まい)も余っているからと、お二人が所有する山に住まわせていただけることになりました。そうして今も暮らす土地に移り住んできたのが2018年8月。僕たち家族の自給自足生活が、いよいよ本格的にスタートしました。
次回(6月26日予定)は、愉快で厳しい僕たちのプレハブライフを紹介します。
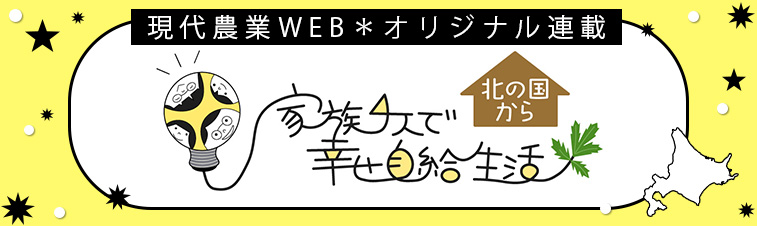
- 第1話(6月12日) 私のパーマカルチャー
- 第2話(6月26日) 極寒のマイホーム
- 第3話(7月10日) 雨漏りとペンキ塗り
- 第4話(7月24日) トイレを手作りする
- 第5話(8月21日) お風呂を手作りする
- 第6話(8月28日) 断熱のお話
- 第7話(9月18日) 我が家の電力自給
- 第8話(9月27日) 北海道大停電 頼りは太陽光発電と人のぬくもり
- 第9話(10月13日) 水を自給する
- 第10話(10月25日) 暖房を自給する(前編)
- 第11話(11月9日) 暖房を自給する(後編)
- 第12話(11月28日) スーパーで野菜を買わない実験
- 第13話(12月15日) みんなで畑づくり 柵の設置、定植
- 第14話(1月5日) ニワトリ小屋づくり(前編)
- 第15話(1月22日) ニワトリ小屋づくり(後編)
- 第16話(2月20日) 食の自給① 梅干し&納豆
- 第17話(2月29日) 食の自給② 麹、味噌、醤油
- 第18話(3月15日) 食の自給③ 冬を乗り切るための漬け物づくり
- 第19話(4月9日) 食の自給④ 薪ストーブを使ってつくる干し野菜&おやつ
- 第20話(5月16日) 服作り(前編)
- 第21話(6月24日) 服作り(後編)
- 第22話(9月13日) 石けん作り
- 第23話(10月21日) 暮らしから学ぶ
- 第24話(12月17日・最終回):旅から学ぶ
本連載が、単行本になりました!

北海道札幌市の山奥で「パーマカルチャー研究所」を運営。パーマカルチャーとは、持続可能な暮らしのこと。家族4人で自給自足の暮らしをしながら、その暮らしから得られたパーマカルチャー的価値観を伝えることを仕事としている。著書『北の国から 家族4人で幸せ自給生活』(農文協)が発売中。
(写真提供:金本綾子)
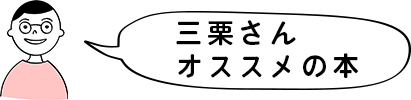
小さいエネルギーで暮らすコツ
太陽光・水力・薪&炭で、電気も熱も自分でつくる
農文協 編
輸入任せのエネルギー問題を再考!ミニ太陽光発電システムや庭先の小さい水路を使う電力自給、熱エネ自給が楽しめる手づくり薪ストーブなど、農家の痛快なエネルギー自給暮らしに学ぶ。写真・図解ページも充実。
パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン
ビル.モリソン 著
田口恒夫 訳
小祝慶子 訳
都市でも農村でも、自然力を活かして食物を自給し、災害に備える農的暮らしの環境調和型立体デザイン。農地、家まわりの土地利用、水利用、家屋の建て方まで具体的に解説。経営システム全体で環境への適応をめざす。