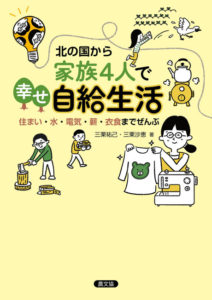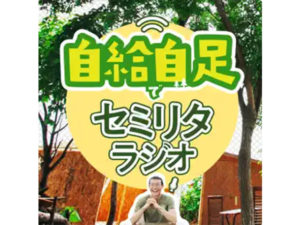北海道・三栗祐己
北海道の山の中で、住まいや電気(太陽光発電)、水道などを自分たちでつくりながら、働きすぎず、穏やかに、豊かに暮らしている三栗さん一家のお話です。
2024年7月、この連載をベースにした単行本『北の国から 家族4人で幸せ自給生活』が発売されました。

「自給自足だと、学校とかはどうするの?」
そんな質問をいただくこともありますが、学校は歩いて通える距離にあります。でも、山暮らしをしていると、教育や子育てについても、色々なことを考えます。今回は、そんな「教育と子育ての自給」についてのお話です。
生きる力と生き抜く力
教育と言えば、まずは学校が思い浮かびますよね。学校教育のカリキュラムの基準として、文部科学省では「学習指導要領」というものが定められています。学習指導要領では、「生きる力」がキーワードになっています。
生きる力とは何か。あらためて考えると難しい気がしますが、ぼくは今の山暮らしをするまでは、
「生きる力=お金を稼ぐ力」
のような気がしていました。生きていくにはお金が必要で、やっぱりその額は、たくさんあった方がいい。お金をたくさん得るためには、いい会社に入らなきゃいけない。いい会社に入るためには、いい大学に行かなければいけない。いい大学に行くためには、いい高校に行かなければ。いい高校に行くためには、いい中学……いい小学校……いい幼稚園……?ぼくは北海道に住んでいたので、中学までは公立に通っていましたが、首都圏などに住んでいると、幼稚園から「お受験」があると聞きます。そうしていい会社に入ったとしても、今度は朝から晩まで、働かなければいけない。いつしか、家族を守る、養うための仕事が、家族を犠牲にして仕事をしている自分に気がつき、これはどうしたらいいものかと思い悩みました。
おかしい。
一生懸命勉強して、いい高校、いい大学、いい会社に入ったはずなのに……。けっこうちゃんと「勉強」してきたはずなのに……。
「何かが根本的に違う気がする……」
そんな紆余曲折があり、ぼくは勤めていた仕事を辞めて、タイのパーマカルチャー・ファームに家族で長期滞在することになりました。(第1話参照)この、自給自足の暮らしをするファームに来たとき、日本とは根本的に生き方が違うと感じました。タイには子どもたちも一緒に行っていたこともあり、ぼくたち家族は毎週金曜日、全児童15人程度の、村の小さな学校を訪問させてもらっていました。


そこでは、簡単なかけ算ができない中学生がいるなど、お世辞にも学力が高いとは言えない状況でした。「日本の学力はトップ水準」と聞くこともありますが、確かに日本の学力は高いのかも知れない、そんなことも思いました。でも彼らは、ぼくたち日本人にはない、こんな能力を持っていました。
- 14歳にして小屋を自分で建てられる
- 畑づくりの授業では、指示がないのに、全員で協力しながら次々と畑を耕していく
- その授業で、7歳の少女が、自ら近所の養豚場に行って、畑の栄養になる豚のフンをバケツいっぱいにもらってくる
- タイ語の通じないうちの子どもたちにも、積極的に話しかけて、自分たちの遊びに誘う高いコミュニケーション能力
- 沼に入ってカニを捕ってきて、それを自分たちで火起こしして、調理して食べる
僕は彼らの「生き抜く力」の高さに、感動しました。






タイの村での彼らのライフスタイルは、ただ暮らしているだけ。ですが、家や食べ物など、暮らしに必要なモノは自ら作り出していました。タイの子どもたちは、そんな日々の暮らしから、この「生き抜く力」を身につけていたのでしょう。日本が、必要なモノを「買う暮らし」だとすれば、そのタイの村では、必要なモノを「作る暮らし」をしていたのです。

遊暮働学(ゆうぼどうがく)のライフスタイル
彼らは日々、ただ暮らしていました。でも同時に、暮らし自体を、遊ぶように楽しんでもいました。同時に、暮らしの中で働いてもいましたし、さらには同時に「生き抜く力」を学んでもいました。遊び、働き、学びが、暮らしと完全に一体化していたのです。
例えば、彼らは、木や竹や草から、家を自分たちで建ててしまいます。暮らしに必要な「家づくり」という働き(仕事)。それ自体が、みんなでやる遊びのように楽しくもあり、同時に家の作り方を学ぶことにもつながっていました。日常の暮らし、あらゆることがこんな調子ですから、彼らは究極的にいえば、暮らしているだけで暮らしが回っているのです。ぼくはそんな彼らの暮らしに憧れ、自分もそんな風に生きてみたいと思いました。そして、このすばらしい暮らしを、過去の自分と同じように生き方に違和感を感じる人に伝えたい、とも思いました。
そこでこうした暮らしを表す端的な言葉を考え、遊び、暮らし、働き、学びの字を取って、「遊暮働学(ゆうぼどうがく)」と表現することにしました。



暮らしのなかでの学び
日本での買う暮らしに対し、タイでの作る暮らし、「遊暮働学」。
もちろん、全てを作る暮らしにはできませんし、お金を使わずに生きることは、不可能です。でも、暮らしの一部分だけ、例えばご飯を作るという小さな部分からでも、遊暮働学を少しずつ実践することはできるでしょう。その「作る範囲」を少しずつ広げていけば、暮らしの中の遊暮働学の割合を増やすことはできます。
考えてみると、暮らしを作るという意味では、家事と言われる、
- 炊事(料理)
- 洗濯
- 掃除・片づけ
も、立派な遊暮働学です。家事代行という形でお金を払って依頼できることを、自分でやっているからです。そう考えると、遊暮働学していない人はいない、とも言えるでしょう。わが家はそれに加えて、自給自足の山暮らしをしていますので、
- 畑仕事
- 家や電気・水道のメンテナンス
- 梅干し作り
- 漬け物作り
- 薪づくり
- ニワトリの世話
- 薪運び
- 雪かき
なども、遊暮働学の要素として入ってきています。
遊暮働学しませんか?

このように、暮らしの中で家事をすることは、「作る暮らし」、遊暮働学の第一歩です。普段やっている家事を、
- 子どもと一緒にやる
- 子どもにお願いする
ことは、遊暮働学という「教育・子育ての自給」になるのではないでしょうか。子どもがうまくできない場合には、教えたり、一緒にやってあげれば、親子のコミュニケーションにもなります。自分でやってみることで、家事の「ありがたみ」を感じるようにもなるでしょう。


子どもは、いずれ大人になって家を出ていきます。そのとき初めて、家事をする必要に迫られ、アタフタするかも知れません。それよりは、小さいうちから、一緒に家事をするという遊暮働学の実践が、子どもの「生き抜く力」になるのではないでしょうか。


次回(最終回)は、旅から得た「生き抜く力」についてです。お楽しみに。
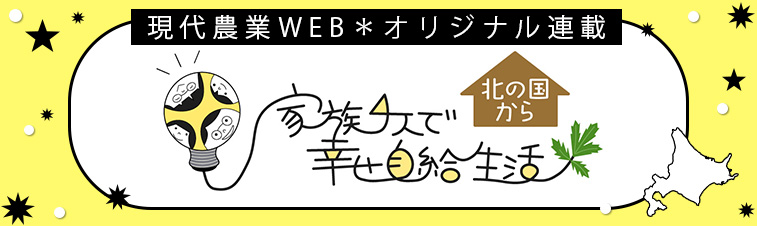
- 第1話(6月12日) 私のパーマカルチャー
- 第2話(6月26日) 極寒のマイホーム
- 第3話(7月10日) 雨漏りとペンキ塗り
- 第4話(7月24日) トイレを手作りする
- 第5話(8月21日) お風呂を手作りする
- 第6話(8月28日) 断熱のお話
- 第7話(9月18日) 我が家の電力自給
- 第8話(9月27日) 北海道大停電 頼りは太陽光発電と人のぬくもり
- 第9話(10月13日) 水を自給する
- 第10話(10月25日) 暖房を自給する(前編)
- 第11話(11月9日) 暖房を自給する(後編)
- 第12話(11月28日) スーパーで野菜を買わない実験
- 第13話(12月15日) みんなで畑づくり 柵の設置、定植
- 第14話(1月5日) ニワトリ小屋づくり(前編)
- 第15話(1月22日) ニワトリ小屋づくり(後編)
- 第16話(2月20日) 食の自給① 梅干し&納豆
- 第17話(2月29日) 食の自給② 麹、味噌、醤油
- 第18話(3月15日) 食の自給③ 冬を乗り切るための漬け物づくり
- 第19話(4月9日) 食の自給④ 薪ストーブを使ってつくる干し野菜&おやつ
- 第20話(5月16日) 服作り(前編)
- 第21話(6月24日) 服作り(後編)
- 第22話(9月13日) 石けん作り
- 第23話(10月21日) 暮らしから学ぶ
- 第24話(12月17日・最終回):旅から学ぶ
本連載が、単行本になりました!

北海道札幌市の山奥で「パーマカルチャー研究所」を運営。パーマカルチャーとは、持続可能な暮らしのこと。家族4人で自給自足の暮らしをしながら、その暮らしから得られたパーマカルチャー的価値観を伝えることを仕事としている。著書『北の国から 家族4人で幸せ自給生活』(農文協)が発売中。
(写真提供:金本綾子)
住まい・水・電気・薪・衣食までぜんぶ
三栗祐己・三栗沙恵 著
衣食住の生活技術や水・エネルギーの自給で、豊かで楽しい暮らし。プレハブの住まい、オフグリッド太陽光発電、薪ストーブ、野菜の貯蔵や保存食作り、衣類や石けんの手作りなど、「自給生活」を楽しむコツを大公開。