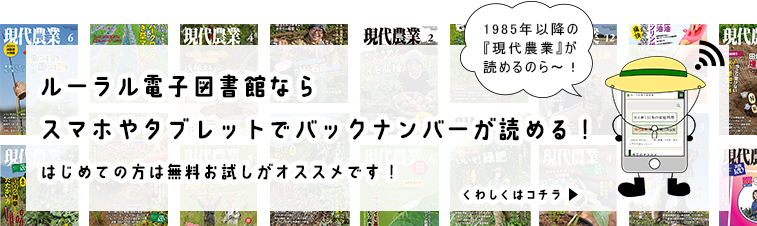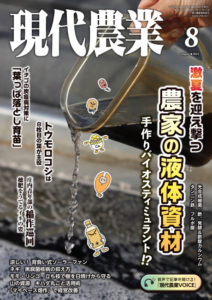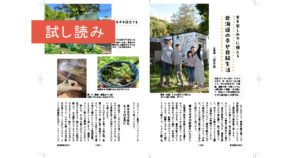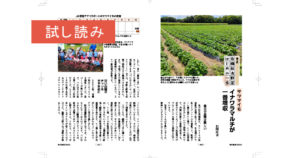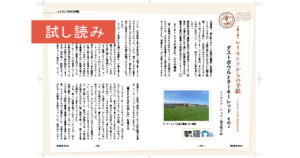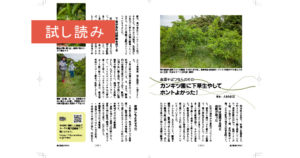北海道で、畑を耕さない「大地再生農業」を実践するレイモンドさんが、3歳の孫のあやめちゃんに綴る物語。150年前に、ご先祖たちがウクライナからアメリカへ持ってきたターキーレッド小麦は、またたく間に全米に広がった。しかし、時代とともに姿を消してしまう。開拓民が草原で農耕を始めて約70年後の1930~40年代、土壌の劣化に伴う激しい砂嵐が頻発するなか、農家は工業的な農業への転換を迫られていた──。
レイモンド・エップさんが書いた原文(英語)はこちらでご覧いただけます。
レイモンド・エップ/荒谷明子訳

ターキーレッドが消えた、二つの理由
違う品種同士をかけ合わせてつくる一代交配のトウモロコシは、それまでの在来種より2倍の実をならせることができた。栄養をたっぷり必要とするトウモロコシも、化学肥料を使えば毎年同じ土地で育てることができるようになった。しかも、地下から水を必要なだけ汲み上げられるようになったから、雨が降らない年でも安定してたくさんの量を収穫できるようになったんだ。
そこで、ご先祖たちも周りの農家も、小麦を育てるのをやめて、もっとお金になるトウモロコシだけを、毎年同じ土地でつくり続けるようになった。これが、ターキーレッドが農村から姿を消した理由の一つだ。
もう一つの理由は、どう説明したらいいかな。ターキーレッドの背が高かったから、と人はいうかもしれないけれど、ターキーレッドのせいではなかったよ。世界は破滅的な戦争から立ち直りつつある時期だった。飢えている人々に食べ物を届ける使命があると農家は感じていた。そしてつくればつくるだけ売れたから、農家は化学肥料や農薬やかんがい技術を取り入れて、どんどん収穫量を増やし農地を広げていった。
化学肥料を使うとターキーレッドは徒長してしまう。徒長というのは、作物の背が伸びすぎること。すると、実が太り始めるとその重さで株が倒れてしまうよね。そこで育種家たちは、背が低く、肥料をやっても倒れない新品種の小麦をつくり始めた。 そして、安価なチッソ肥料で栽培されたこれらの新品種の収量は、ターキーレッドよりもはるかに多かった。
「豊かさのなかの苦しみ」を考える
こうしてターキーレッドをつくる人は、やがてほとんどいなくなってしまった。その当時、人々は失ったものについて、あまり深く考えることはなかったかもしれない。でもね、君のひいおばあちゃんが教えてくれたけれど、1930年代の人々の「貧しさのなかでの苦しみ」を話すときに、ひいひいおじいちゃんはいつも、次の時代の人々は「豊かさのなかの苦しみ」を味わうだろうといっていたそうだ。
ジイジは、ひいひいおじいちゃんはどんな意味でそういったんだろうって、ときどき考えることがあるよ。前に話したように、君のご先祖たちは、お金や権力の魅力になびかない強い信仰を持って、神さまを信じる群れとして生きようとしてきた。
でも、新しい技術を取り入れていったことで、知らぬ間に暮らしは大きく変化してしまった。大きなトラクタを使って肥料と農薬で管理する農業を追求した結果、人と人とのつながりは薄れていき、大地や生きものたちへの眼差しも変わっていった。信仰は一人ひとりの心のなかの出来事のように扱われるようになった。
「豊かさのなかの苦しみ」について、ジイジはこんなふうに考えることもある。暮らしは豊かになったけれど、土もそこに育つ作物もそれを食べる人も、徐々に健康が損なわれているんじゃないかってね。昔ほど土を耕さないように意識されてきているにもかかわらず、土の団粒構造が崩れて風で飛ばされたり、雨が降ると土が流れやすくなっている。 1930年代のような砂嵐がここ数年で再発しているんだ。

タネを育てることで、先祖の物語に出会う
あやめちゃん、人間であることは難しいことかもしれない。一人で人生を歩まなければならないとしたら、2倍大変だ。だから君は、家族やコミュニティの一員であることを忘れないでほしい。コミュニティとは人だけでなく、土地もそこに棲む生き物も含まれていることを感じてほしい。私たちは、遠い過去からご先祖たちが経験してきた多くの物語を持っている。見る目と聞く耳を持っていれば、土地もたくさんのことを私たちに語りかけてくれるよ。
過去から学ぶことは、過去の失敗を繰り返さないだけでなく、新しいことに向かってこれまでとは違う方法を見つけ出そうとするときにも役立つだろう。ターキーレッドを育てることで、ジイジはたくさんの物語に出会ってきた。ご先祖の物語だけじゃなくて、世界中の人々の暮らしにも共通する物語があるってことも知った。
今朝、畑に行ってみたら、ターキーレッドが雪の下からみごとに姿を現わしていた。肥料を与えていないにもかかわらず、しっかりとした緑色をした美しい姿を見て、体の中からこみ上げてくるものを感じたよ。これらのタネは自分を過去と結びつけてくれている。そして、今を生きる自分を養ってくれている。未来への希望をも与えてくれている。
このタネが、そしてタネが育んできた物語が、きっと君を力づけてくれますように。(北海道長沼町)
冬に手作業で地下水を掘り上げた

1937年の冬、ジイジが生まれる20年以上前のこと、ジイジの故郷のヘンダーソンで3人の青年たちが、地面に穴を掘りはじめた。簡単な三脚と滑車を作ってその先にバケツを吊り下げ、交代で土を掘ってはバケツに入れ、ほかの2人が土を運び上げては捨てていく、単純だけど大変な作業だ。冬の寒さの中でも汗を流しながらの大仕事だ。掘っても掘ってもなかなか探しているものが見つからなかった。
しかし、とうとう地面から45m掘り進んだところで砂利の層に出くわした。この砂利の層は厚さが30m以上あり、大量の水を含んでいた。そう、彼らが探していたのは水だったんだ。地下から水を汲み上げて作物に水をやるためにね。
*
水は生命だ。1930年代は、ひどい干ばつでみんなが苦しんでいたころだったから、これは神さまからの贈り物だ、これで生きていくことができると喜ぶ人が多かった。かんがいをいち早く導入した人たちは、たくさんの収量をあげて裕福になり、農地をどんどん増やしていった。
でもね、ヘンダーソンのある指導者は、その様子を見て地域社会が変わっていくことを心配していた。たとえば、一軒あたりの農家が持つ農地が2倍になったとする。そうすると、町全体の農家の数はどうなると思う? 半分に減ってしまうよね。
土地を失った人の多くは町から離れていくことになる。規模を増やすのではなくて、みんなが適正規模で丁寧に農業をすれば町の人口も守られるし、次の世代の農家にも機会を提供できるだろう。そんな将来を彼は望んで人々に警告した。けれど、残念ながら聞き入れられることはなかった。
レイモンドさんが書いた原文(英語)は、こちらでご覧になれます。
試し読み
作ってみた!手づくりバイオスティミュラント
取材動画(期間限定)
動画は公開より3カ月間無料でご覧いただけます。画像をクリックすると「ルーラル電子図書館」へ移動します。
「現代農業VOICE」のお試し視聴
「現代農業VOICE」は、記事を音声で読み上げるサービスです。画像をクリックするとYouTubeチャンネルへ移動します。




 あわせて読みたい
あわせて読みたい