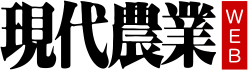2025年3月10日発行の『みんなの有機農業技術大事典』。この連載では大事典にご寄稿いただいた著者の方々に、内容のエッセンスをご紹介いただきます。2回目は、元國學院大学の久保田裕子さん。
2024年10月号「主張」「『みんなの有機農業技術大事典』発行にむけた思い」もぜひご覧ください。
久保田裕子

推進法を記念、有機農業の日
「12月8日って、何の日か知っていますか? 『有機農業の日』です」というポスターがあちこちに配られたのは2016年秋のこと。この年、06年の「有機農業推進法」(以下、推進法)成立からちょうど10年になるのを記念して、集会を上野水上音楽堂で開くとともに、関係した5団体が「有機農業の日」として記念日登録したのです。
推進法は、旧食料・農業・農村基本法(1999年)第32条「自然循環機能の維持増進」の規定を取り上げて、国・地方自治体が総合的施策で有機農業の推進に取り組まなければならないとした環境農業政策の理念法です。国においては有機農業推進基本方針が策定され、都道府県・市町村では有機農業推進基本計画の策定により、積極行政を行なう責務があります。
推進法の成立は、長年有機農業に取り組んできた人々にとって感激の瞬間でした。成立に至る国会審議は、両院それぞれの農林水産委員長が提案し、本会議でも全会一致、ただちに成立というめざましいものでした。
まさに市民立法
推進法成立に至るまでには、長い検討の経緯があります。有機農業運動の身近にいた研究者らによる研究から始まり、05年8月には日本有機農業学会(1999年設立)内の有機農業政策研究小委員会が、35年に及ぶ運動の成果を汲み、条文にまで及ぶ『有機農業推進法試案』を策定・公表しました。有機農業推進議員連盟はこの試案をたたき台にし、その骨子のみを活かし推進法として法制化したのです。
国会審議の前に推進議員連盟は17回にわたる勉強会や立法作業部会、2回の現地視察、シンポジウムを行ない、具体的な法案の検討も重ねた末の国会上程でした。まさに市民立法の法律といえます。
みどり戦略にも大いに影響
2021年には、2050年時点のあるべき目標「重要業績評価指標」(KPI)14項目を挙げた「みどりの食料システム戦略」が策定されました。この本文の筆頭に1化学農薬使用量をリスク換算で50%低減、2化学肥料の使用量を30%低減、そして3として、有機農業(国際水準)の取り組み面積を耕地面積の25%、面積にして100万haにすることが挙げられました。
地球環境の限界値をみた「プラネタリー・バウンダリー」によると、生物多様性の劣化、そしてリンとチッソの循環は、持続可能な限界をゆうに超えています。有機農業拡大を掲げるのは当然です。日頃の危機感からみると、むしろ25%は低いくらいですが、いずれにしても「有機農業」がこうした戦略俎上に上るのも、推進法があったればこそといえるでしょう。
『大事典』でさらに有機普及を
このほど、農文協より『みんなの有機農業技術大事典』が刊行されることになり、喜ばしい限りです。
この『大事典』刊行にも大いに携わった「日本有機農業研究会(以下、日有研)」では、これまでにいくつか有機農業の理念に立った実践に役立つ本を刊行してきました。たとえば、会員70名近くが土づくりから食べ方までにわたり執筆した『有機農業ハンドブック』(1999年、農文協)。今や古典となりつつありますが、いまだに有機農業の深化・拡大に貢献しています。
日本は推進法というすばらしい法律を持ちながら、制定して20年近く経っても有機農業の面積は1%未満と、上記KPIの25%からほど遠いのが現状です。しかし、各地での実践の蓄積があり、実践から導き出された技術もあり、また、推進法制定後は徐々に行政機関での有機農業研究も行なわれるようになっています。
今回の『大事典』はまさにそれらの官・民技術の集大成であり、大いに期待しています。
日有研を立ち上げた一楽照雄

上記の日有研は、1971年に日本の有機農業の草分けとして結成されました。「有機農業」という言葉は、その時点で日本にありませんでした。
創立に奔走した一楽照雄は、農林中央金庫理事、全国農業協同組合中央会(全中)常務理事などを歴任した後、66年からは(財)協同組合経営研究所(現・JC総研に統合)の理事長を務めていました。『一楽照雄伝』(普及版は『暗夜に種を播く如く』、農文協)には、日有研創設に至る決断は「迅速果敢」なものだったと書かれています。
日本農村医学会を立ち上げて活動していた長野県の佐久総合病院院長・若月俊一、食べものと健康のつながりから1959年に『農薬の害について』を著していた奈良県五條市の医師・梁瀬義亮らに背中を押され、一楽は研究会の結成を決意します。

一楽はまた同時期に、東京農業大学教授(土壌学)の横井利直から、アメリカで有機農業に取り組む人々がいることを紹介されます。イギリスではアルバート・ハワードの『農業聖典』(1940年)、アメリカではジェローム・I・ロデイルの『Pay Dirt』(45年)が有機農業運動の理念・原理・農業技術などを述べた指導書になっていることがわかりました。
『農業聖典』の邦訳本は、59年に農林水産業生産性向上会議から刊行されており、その「跋」は元協同組合経営研究所理事長だった石黒忠篤が書いていました(2003年に日有研が保田茂監訳で発行、コモンズより)。
一方の『Pay Dirt』は、50年に酪農学園大学から『黄金の土』という絶妙なタイトルで刊行されていました(後に一楽照雄訳『有機農法―自然循環とよみがえる生命』として日有研が発行、農文協人間選書)。これらがすでに邦訳・出版されていたことは、大いに一楽の発想の助けとなりました。
天地有機
『黄金の土』を刊行した酪農学園大学の前身「野幌機農学校」を創立したのは、北海道議会や戦後国会議員を務めた政治家の黒澤酉蔵(1885~1982年)です。現・雪印メグミルクの創立者でもあり、「北海道酪農の父」と呼ばれています。
新しい研究会を創立するに当たって一楽は、結成趣意書を起草し終わっても会の名称をどうするか、考えあぐねていました。そこで、千葉に閑居していた黒澤を訪ね、機農学校に使われている「機」について尋ねます。
黒澤は「『機』とは、天地経綸というか大自然の運行のこと」と答え、「機を知るは農のはじめにして終りなり」と機農学校の門に掲げていると答えます。一楽はそれを「天地、機有り。」、すなわち東洋の自然観・農業観を表わすと会得し、研究会の名称に「有機農業」と冠することに確信を得ました。
一楽はまたその折に、黒澤の「健土健民」思想の原点が足尾銅山鉱害事件を闘った田中正造(1841~1913年)に師事した4年間にあることを知りました。つまり「有機農業」の源流は、黒澤からさかのぼり「真の文明ハ山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さゞるべし」と訴えた田中にまで至ることができるでしょう。


日有研結成、各地でも活動勃興
1971年10月17日、日有研は会の名称に「有機農業」を掲げ、「環境破壊を伴わず地力を維持培養しつつ、健康的で味のいい食物を生産する方法を探求し、その確立に資する」ことを目的として結成されました。この1971年という年は、日本の農政がいわゆる「農業の近代化」や「近代農業」推進へと大きく舵を切った旧農業基本法(61年)制定からちょうど10年。すでにその破綻は明らかでした。
結成趣意書は、「科学技術の進歩と工業の発展に伴って、わが国農業における伝統的農法はその姿を一変し、増産や省力の面において著しい成果を挙げた」で始まります。しかし続けて、「このいわゆる近代化は、主として経済合理主義の見地から促進されたものであるが、この見地からは、わが国農業の今後に明るい希望や期待を持つことは甚だしく困難である」と喝破。そして「変貌した農業のあり方を根本から問い直し、一旦、伝統的農法に戻って、そこから出直し、もう一つの道を歩もう」と呼びかけました。
以降、各地でそれぞれの「有機農業研究会」がつくられ、地域での活動が始まりました。72年には早くも木次有機農業研究会(島根)が結成され、翌年からは高畠町有機農業研究会(山形)、兵庫県有機農業研究会などが活発な活動を繰り広げました。
食の安全を求める消費者運動も盛んな時代で、双方の出会いは「生産者と消費者の提携」(産消提携)の取り組みを生み出しました。「顔のみえる関係がだいじ」というフレーズが生まれたのもこの取り組みの中からです。

世界語になったTEIKEI
78年に、一楽は各地の活動を担うリーダーたちを集めて「生産者と消費者の提携の方法(提携10か条)」をとりまとめ、日有研の総会で発表し、その後の活動の指針としました。
その第1条では、「生産者と消費者の提携の本質は、物の売り買い関係ではなく、人と人との友好的付き合い関係である。すなわち両者は対等の立場で、互いに相手を理解し、相扶け合う関係である」と、協同組合精神に立つ農産物の「脱商品化」の理念を打ち出しました。「提携」は、農業生産者が主体性を発揮して持続性のある農業を行ない、消費者が環境を含めて安全・安心な食べ物を継続して入手することができるしくみなのです。
世界にグローバル経済が広がり、農業が「工業型農業」へと変貌している中で、この「提携」と同様の理念と方法をもつアメリカのCSA(コミュニティ・サポーテッド・アグリカルチャー)が80年代半ばから始められ広がっています。フランス、ドイツ、ポルトガル、イタリアなどでもそれぞれCSA型の取り組みが行なわれており、日本の「提携10か条」は先駆的事例としてよく知られ、そのまま「TEIKEI」と呼ばれています。
国際有機農業運動の場では、80年代半ばから台頭してきた中南米発アグロエコロジー運動も合流し、グローバルな大企業による工業型農業への対抗力をつくりだしています。
今一度「民」の有機を見直そう

今年5月、改正食料・農業・農村基本法が成立し、8月からは食料・農業・農村基本計画の策定へ向けた審議が始まりました。「生産性の向上」と「効率化」のためとして、先端的テクノロジーの推進が目立ちます。
ここまで見てきた通り、日本の有機農業は民間の研究者・農家による運動がリードして、発展させてきたものです。官製の「有機農業」によって本質が損なわれないよう、注意しながら進める必要がありそうです。
(元國學院大学)
著者紹介:久保田 裕子(くぼた ひろこ)
1949年生まれ。国民生活センター調査研究部勤務を経て、96年から國學院大学経済学部で教鞭を執る。消費者運動、有機農業運動に長年尽力し、現在はNPO法人 日本有機農業研究会の副理事長を務める。
『みんなの有機農業技術大事典』のご案内
化学肥料や農薬を減らそうと農家や研究者が試行錯誤して紡いだ有機農業の技術。本書はその集大成である。
「共通技術編」では、有機農業の歴史や世界での広がり、地球温暖化防止や生物多様性維持に果たす役割のほか、緑肥や天敵利用、不耕起栽培や微生物活用などの基本技術を紹介。モミガラや米ヌカ、堆肥などの有機資材、納豆や米ヌカ、石灰や木酢液を利用した防除技術も解説する。
「作物別編」では、水田や畑作物、野菜や花、果樹や茶、畜産の技術を品目ごとに網羅。執筆者約300人、農家約150人が登場する、みどり戦略時代必携の書である。