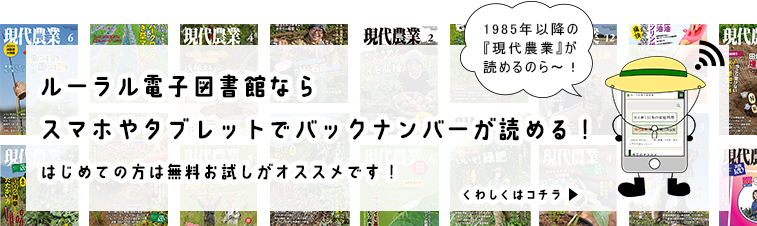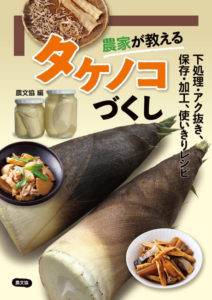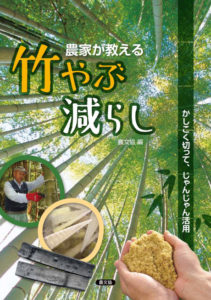伸びすぎたタケノコ「幼竹〈ようちく〉」でつくるメンマが各地で大人気。竹活〈たけかつ〉の一環で広まり、「竹菜」という呼び方も生まれました。ますます注目のメンマをもっとおいしくするワザをご紹介します。
長野・伊藤隆子

幼竹が使える!
長野県南部の主に飯田市にて竹林整備を中心に活動する「NPO法人いなだに竹Links〈チクリンクス〉」で、メンマ商品に関する担当をしております伊藤と申します。法人名の「いなだに」とは伊那谷のことで、南アルプスと中央アルプスに挟まれ天竜川が流れる地域を指します。私たちはこの山と川の自然に恵まれた地で、里山の維持と水源涵養の保全を目的に竹林整備を行ない、メンマ商品「いなちく」を製造しています(2024年4月号p46、他)。

「幼竹」(2mほどに伸びすぎたタケノコ)を食べることが竹林整備につながる、ということを知った時は衝撃でした。当時はまだこの食材について認識している人は少なかったかと思いますが、今では全国的に認知され、幼竹を使ったメンマづくりを推奨している団体「純国産メンマプロジェクト」の加盟者は40都府県152団体にのぼっています(2024年12月時点)。
これまで取り組む中で、幼竹を使ったメンマづくりには多くのコツがあると実感しています。タケノコの扱い方とも違います。幼竹の特性を理解してみなさんにおいしいメンマをつくっていただきたいと思います。ここでは孟宗竹の幼竹を使う場合について紹介していきます。
幼竹の収穫
▼なまくら刃で膝上を切る
1.5~2.5mほどの幼竹を見つけたら、膝の上、地表から50cmの部分を目安に刈り取ります。ノコギリや鎌で簡単に切ることができます。
地表に近い部分は木化して硬いので、切れ味のよい刃物を使うと食べるには硬すぎる部分も一緒に切り取れてしまいます。ここでのコツは、少しなまくらな刃物を使うこと。それでも切れるくらいの柔らかい部分を狙うとよいでしょう。
穂先については、先20~30cmは食べられない皮だけなので現場で切り落としておくと後の処理がラクです。

▼丁寧に扱う
幼竹の可食部分は柔らかく、収穫したものを落としたり投げたりすると砕けて割れてしまうので、運搬時も気を付けましょう。
皮剥ぎ
▼産毛があるから完全除去
幼竹はタケノコと同じようにしっかりとした皮を被っています。縦に皮の厚み分の包丁を入れ、横向きにバリバリと剥いでいきます。
皮は食べられないので廃棄します。竹の皮を包装紙代わりに使っているのを目にすることもありますが、それは「真竹」という種類の竹の皮です。孟宗竹の皮には大量の産毛がついており、包装紙にすると産毛が中身に混入してしまうので使えません。私たちは畑に埋めています。畑のマルチにしたり、紙の原材料にしたりと利活用を探っている方もいらっしゃいます。

節取り&仕分け
▼節と紫色の部分は取る
皮を剥ぐと、美しい黄緑色の可食部が現われます。竹へと生長中なので、節がついています。節の直下は紫色で、そこから次の節まで黄緑色のグラデーションに色づいています。節の部分と紫色の部分は硬いので食べられません。残念ながら廃棄します。
この部分も畑に入れるとよい肥料になります。かなりの糖質と乳酸菌を含んでいるため、そのまま廃棄すると発酵臭と大量の虫が発生しますが、土をかぶせておけば大丈夫。私たちは事務所の畑に埋めてダイコンを栽培したところ、埋めなかった年と比べて大きなダイコンがとれました。

▼包丁の刃の入り方で判断
紫色からのグラデーション部はどこから可食部かわかりにくく苦労します。見分ける方法としては、紫色の部分に包丁をあて、ナシやリンゴを切るくらいの力加減で徐々に黄緑色の部分に近づけていき、スパンと切り落とせる箇所からが可食部です。
硬すぎるかどうか不安に思ったら、かじって確かめてもよいです。適していない箇所は筋張っているのですぐにわかります(飲み込むとアクで胃痛になるので吐き出すこと)。
穂先の部分になると節に紫色はついていません。内部についている節間のペラペラした部分はゆでてもすじっぽいのでこれを取り除けば、全部食べられます。


▼部位ごとに仕分ける
幼竹の元部・中央部と比べると、穂先はかなり柔らかく、のちほどの工程のアク抜きの時間も違います。商品化したり調理にこだわりたい方は選別しておいたほうがよいでしょう。
円筒状になった可食部は、繊維に沿って2~3分の1に縦割りするか、縦長の一口大にカットします。サイズはなるべく均一にしたほうが、アク抜きや脱塩工程が均等に仕上がります。

ゆで
▼米ヌカは使わない
たっぷりのお湯でゆでてアクを抜きます。幼竹がお湯の中で踊るくらいの湯量が目安です。米ヌカなどは使いません。原材料に残留して、保管時の腐敗の原因になるからです。
▼部位ごとに時間を変える
元部・中央部は沸騰してから40分頃に味見をします。アクがまだ残っていたら5分ごとに味見をします。ただし60分以上はゆでません。竹本来の甘みが抜けてしまうからです。穂先は20~30分程度でアクが抜けます。ゆでている間はアクをこまめに取りましょう。
塩漬け
▼いったん洗う
ゆで終わって湯切りしたら、私たちは流水で一度洗浄しています。高温のまま塩漬けする方法もありますが、商品に皮の産毛が入って異物混入となってしまったことがあるので、商品化する場合は気を付けたほうがよいかと思います。
漬物樽には厚めの漬物ポリ袋を敷いておきます。湯切りした幼竹を計量し、「幼竹:塩=10:3」となるように塩を用意します。例えば幼竹20kgに対し塩6kgです。
そして樽の袋の中に、塩、幼竹、塩、幼竹とミルフィーユ状に漬けていきます。一杯になったら袋の空気をゆるく抜き封をして、中蓋、重石を置き、蓋をします。重石の重量は原材料に対して20~40%を目安とします。
▼ここまでを1日でやる
幼竹はタケノコと同じく、収穫した瞬間からアクが増え始めるので、収穫から塩漬けまで1日のうちに行なっています。大量に処理するには人手がいるので、収穫量をコントロールすることも必要です。
塩漬け後は一昼夜で水が上がってきます。原材料がすべて塩水に浸かると安定します。もし2日経っても水が上がらなければ、重石を増やすか30%濃度の塩水を追加してください。ここから1カ月漬け込みます。この塩分濃度であれば、冷蔵で1年は保存できます(常温で保存する方もいますが、カビが生えることがあります)。


脱塩
▼抜きすぎ注意
食べる分だけ樽から出して、一晩かけ流しの流水で塩抜きします。脱塩の塩梅は、中心部に若干の塩気が残っているくらいがちょうどいいです。あまり長時間行なうと、ゆでの時と同じように竹の甘みが抜けてしまいます。
調味
▼加工業者と相談する手も
脱塩した幼竹は、メンマ風の味付けはもちろん、そのままパスタやサラダの具材としても使えます。シャキシャキとした食感を楽しめますので、ぜひ想像力を働かせてさまざまな料理に活用してみてください。商品化を考えていらっしゃる方は、惣菜や漬物の製造許可を持っている食品加工事業者に相談してみましょう。
「幼竹」「竹菜」と表記したい
加工食品を商品化する場合、商品の裏面に「一括表示」とよばれる表記を貼ることが義務づけられています。この項目の中に「原材料名」があり、本来であればタケノコとは違うアプローチの食材であることから「幼竹」等と記載したいところですが、「いなちく」では「たけのこ」と表記しています。なぜなら、この項目は一般消費者が直感的にわかる表記にしなければならないルールがあり、幼竹という言葉はまだ一般的ではないとの認識だからです。
野菜や山菜という言葉があるように、幼竹をもっと食材として捉えてもらうために「竹菜」という呼称にしよう、という呼びかけも純国産メンマプロジェクトでは行なっています。ほとんどが中国等の外国産で賄われているメンマに対し、国産で安全な食材としてアピールできると思います。一括表示も将来的には「竹菜」という表記で一般消費者が認知できるくらい、この言葉が広がってくれればと願っています。
(長野県売木村)
この記事の詳細については『現代農業』2025年4月号をご覧ください
試し読み(おすすめ記事)
取材動画(期間限定)を見る
動画は公開より3カ月間無料でご覧いただけます。画像をクリックすると「ルーラル電子図書館」へ移動します。
「現代農業VOICE」を聴く
下処理・アク抜き、保存・加工、使いきりレシピ
農文協 編
春を代表する食材・タケノコ。下処理やアク抜き法、水煮や冷凍、塩漬け、乾燥などおいしさを長く保つ保存・貯蔵法、国産メンマづくり、和洋のレシピまで、タケノコを味わいつくす知恵と技を大公開!
かしこく切って、じゃんじゃん活用
農文協 編
幼竹を使ったメンマ(幼竹1本が1万8000円に)、「竹の1m切り」成功のポイント、竹の暴走を防ぐ周囲1~2mの間引き、竹炭、竹パウダー、竹燃料、白子タケノコなど、かしこい竹やぶの減らし方、竹林の整備・活用術。