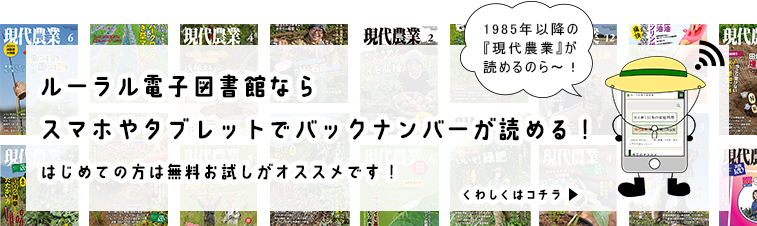緑肥作物の役割が大きく広がっています。堆肥代わりに、有機物を補給するだけでなく、土を被覆し、土壌流亡や高温乾燥を防いだり、耕盤層を壊したり……。さらに、何種類もミックスすると、地下部で草の根や微生物が交流し合い、互いの長所が生き、相乗効果をもたらします。北海道発、農家によるタネの輸入も始まり、2025 年はミックス緑肥が全国に拡大しそうな予感!?
北海道・廣中 諭

2016年に親元就農し、現在8年目です。作付面積は約60haで種子バレイショ(ジャガイモ)、秋小麦、テンサイ、ダイズ、休閑緑肥の輪作を行なっています。2023年より慣行農業のなかにミックス緑肥と省耕起を取り入れ、長期的な土壌環境の改善を目指しています。
キカラシは生育旺盛で結実が早い
23年に播いたミックス緑肥の内訳はエンバク野生種、ソルガム、スーダングラス、ヘアリーベッチ、赤クローバ、キカラシ、葉ダイコン、ヒマワリ、ダイズの4科9種類です(次ページ表)。ミックスした緑肥のタネをムギやダイズに使うドリルシーダーで播きましたが、ダイズはタネが大きく、他の緑肥と同じ播種深度だと浅すぎて乾燥し、発芽不良になりました。
初期生育はとくにキカラシが旺盛で結実も早かったため、雑草化防止のために早期の細断処理が必要でした。その細断によってヒマワリなどの生長点が上にある緑肥も同時に淘汰されてしまいました。しかし、ほかのイネ科やマメ科の緑肥は何度も復活します。植物の根が出す液体炭素(光合成産物)の放出を促す目的で、緑肥の上半分を複数回にわたって細断処理しました。
秋もそのまま育てましたが、赤クローバは寒さに強く再生力も旺盛なため、次作に雑草化する危険があると判断し、11月の細断すき込み時に泣く泣く除草剤をかけました。



ロータリなしでジャガイモを無事収穫
省耕起の取り組みでは、春のスタブルカルチによる荒耕起をやめ、土壌に負担のかかるロータリ作業は、ディスクハローやパワーハローに置き換えました。
春にパワーハローのみで粗め(最大で2cm以下)に砕土・整地した圃場のジャガイモは、収穫・選別作業の際に土塊が邪魔になることもなく、収量も例年以上の3.6〜3.7tとなりました。今後ロータリを使用することはほぼないと思います(以上、23年10月号p78も参照)。
アブラナ科の影響でそうか病発生!?
24年のジャガイモ畑は、前年にミックス緑肥を育てたエリアとダイズ作のエリアが隣り合っていたため、収量の比較を行ないました。
結果は前作がダイズ区よりもミックス緑肥区のほうがコンテナ1基分(約1.4t)多収で、4t以上とれました。ここまで差が開いたのは、ダイズ後で地力を消耗したにもかかわらず、同じ施肥設計としたことも関係しています。ただ、もともと地力の劣る畑であり、従来はよくとれて3.2t程度だったため、ここまでの収量を上げられたことには素直に驚いています。
一方で場所によってそうか病が多発したという弊害もあります。キカラシや葉ダイコンなどのアブラナ科はジャガイモのそうか病を助長させてしまう特性があるため、後作に何を作付けするかによってミックスの内容に注意することも必要です。
収量の違いや病気の発生について、すべてを短絡的にミックス緑肥と関連づけることはできませんが、自分なりの仮説を立てて次年度以降のやり方に変化をつけていくことが重要だと感じます。
無施肥だと地上部の生育が悪かった
前年の反省から24年春のミックス緑肥は開花と結実のタイミングをなるべく合わせるよう、品種を見直しました。キカラシ、スーダングラス、赤クローバ、ダイズをやめ、新たにハゼリソウ、クロタラリアを加えた5科7種類のミックスです(上の表)……
この記事の続きは『現代農業』2025年2月号をご覧ください。
『現代農業』2025年2月号 の「2025ミックス緑肥元年!」コーナーには、以下の記事も掲載されています。ぜひ本誌でご覧ください。
- カバークロップ固定種を輸入 レイモンドさん、タネ屋になる 瀬尾義治
- 土壌消毒も太陽熱処理もなし トマトハウスでミックス緑肥 藤岡省作
- 250haの牧草をミックス緑肥に!の夢が始動 佐藤練
試し読み
取材動画(期間限定)を見る
動画は公開より3カ月間無料でご覧いただけます。画像をクリックすると「ルーラル電子図書館」へ移動します。
「現代農業VOICE」を聴く