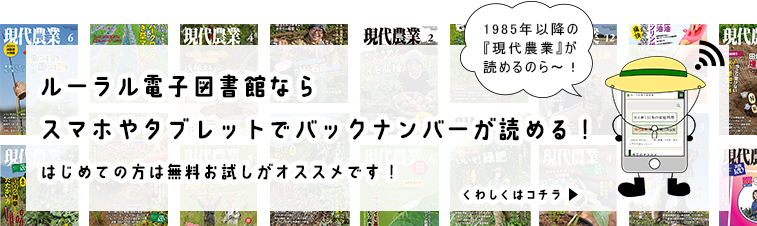近年、猛暑日増加の影響で、晩生品種「新高」や「にっこり」で煮え果が多発しています。一方、農研機構が開発した「甘太」や「王秋」は高温耐性があり、煮え果が発生しませんでした。著者の大澤さんの園では、「甘太」は糖度が15度以上となり、ナシ農家も驚く衝撃の甘さ、「王秋」は甘みと酸味のバランスが最高とのこと。
埼玉・大澤一樹
埼玉県久喜市でナシを1ha栽培している。品種構成は「幸水」から始まり「王秋」で終わる7品種。全量を直売しており、中でも県独自品種の「彩玉」が一番人気だ。

にっこりと新高は壊滅状態
私が住む埼玉県の北部にある熊谷市では、2018年に41.1°Cという日本最高気温を記録した。いつ頃から最高気温35°C以上の猛暑日が増えたのか気になり、気象庁のデータを調べてみると、2000年代に入ってからは猛暑日の増加が顕著で、24年夏は統計開始以降もっとも平均気温が高かったとあった。
猛暑日が多くなった影響で、ここ数年、栽培期間が長い晩生品種の「新高」では果肉が軟らかくなって腐る「煮え果」が大量に発生していた。そのため、23年に見切りをつけて50年以上栽培してきた樹をすべて抜根した。新高ほどではないが、同様に晩生品種の「にっこり」でも23、24年と連年で煮え果が発生。こちらも本数を減らした。


2000年以降に登録された国の品種に活路あり
話は前後するが、新高について調べてみると「1927(昭和2)年に命名」とあり、およそ100年前から栽培されていることがわかった。また、栃木県が開発した「にっこり」は、96年に品種登録されている。2品種とも、猛暑日が増加した2000年以前につくられた品種である。
このような県や個人の育種家が開発した品種と違い、農研機構(国)がつくった品種は、ナシが栽培されているすべての地域で登録前に試験栽培が行なわれている。つまり、猛暑日が増加した2000年以降に登録された品種は、その環境下で試験栽培が行なわれているので、高温耐性があると考えられる。そこでこの間、私の園ではにっこりと新高の本数を減らしつつ、農研機構がつくった「甘太」(15年登録)と「王秋」(03年登録)を増やしてきた。嬉しいことに、現時点ではどちらも煮え果は発生していない。
甘太
ナシ農家も驚く衝撃の甘さ
甘太は、初めて試食した際、その甘さに衝撃を受けた。「素晴らしい品種だ」と思い、18年に一気に改植。実際、私の園でもほとんどの果実が糖度15度以上になる。樹勢は中程度で、花芽の着生が安定しているので栽培も容易。そのうえ、豊産性なのも魅力だ。

青ナシなので、収穫のタイミングを間違えないように気を付けている。というのも、関東ではほとんどの生産者が赤ナシを中心に栽培しているので、収穫色がわからずにとり遅れてしまい、果実の軟化が問題になっているからだ。埼玉県農業技術研究センター久喜試験場では、その対策の一つとして19年にカラーチャートを作成し、生産者へ配布している。私の園ではこれらを参考に、収穫開始後1週間から10日程度ですべての果実をとり終えるように心がけている。

なお、甘太は頂部優勢が弱く、先端が伸びにくい性質がある。そのため、主枝、亜主枝先端をせん定する際には、葉芽の位置で切り返すようにしている。葉芽は春先の動き出しが早いので、樹冠を拡大するうえで有利に働く。予備枝を切り返す際にも同様の管理をしている。
王秋
甘みと酸味のバランスが最高
20年に改植した王秋は、私の園では甘太の後の収穫になる。暑さに強く、甘みと酸味のバランスがよくておいしい。甘太よりも頂部優勢が強く・・・
この記事の続きは『現代農業』2025年2月号をご覧ください
(埼玉県久喜市)
『現代農業』2025年2月号の特集「通用しない従来の暦 品種と播き時 本気で見直すしかない」には、以下の記事なども掲載されています。ぜひ本誌でご覧ください。
- 【ブロッコリー・ダイコン・カブ】今までの常識は捨てて新作型を生み出す(茨城・布施大樹さん)
- 【夏ネギ】梅雨と夏を乗り切る2品種をつくりこなす 吉岡大輔
- 【オクラ】アントシアニンが出ない 秋までやわらかい品種 豊嶋和人
- 【イネ】コシヒカリに苦戦 高温、倒伏に強いにじのきらめきに期待 馬田雄大
試し読み
取材動画(期間限定)を見る
動画は公開より3カ月間無料でご覧いただけます。画像をクリックすると「ルーラル電子図書館」へ移動します。
「現代農業VOICE」を聴く
鶴竣之祐 著
果樹のせん定は難しくない。人気の農業系ユーチューバーが樹の生理を基礎から徹底解説。ブドウ、イチジク、カキ、ミカン、レモン、ウメ、モモ、リンゴなど12種の仕立てや切り方が写真、イラスト、動画でよくわかる。