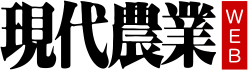8月15日の平和祈念の日(終戦の日)にあわせて、今一度読んでほしい『現代農業』の記事を公開します。今年のテーマは、「知られざる満州」。「五族協和」を掲げ、日本が中国東北部を占領してつくった「満州国」。満州国の生還者や「報国農場」について本を上梓した研究者、『満洲 難民感染都市』の著者らによって執筆された記事を期間限定でお届けします。ぜひご覧下さい。
小塩海平
半分以上の学生が生きて帰れなかった

先般『農学と戦争 知られざる満洲報国農場』(岩波書店)という本を上梓した。この本は、東京農業大学(東京農大)がかつて農学という学問を通して深く関わった「満州報国農場」という国策の全貌を明らかにし、多くの学生を死に追いやった史実について、2人の同志とともに掘り起こしを試みたものである。
東京農大湖北報国農場は1944年(昭和19年)、農業拓殖科の訓練実習地、また満州農業開拓移民の拠点として、現在の中国黒竜江省密山市に創設された。実習と称して送り出された学生は計約90名。しかし、理想郷を築くとされた7000haの土地は、夏は湿地、冬は凍土となり、実際に開墾できたのはわずか3haにすぎなかった。そして終戦後の逃避行や収容所での過酷な生活で、学生56名と教員2名が栄養失調や赤痢、発疹チフスなどで亡くなった。農林省の役人や農学者(東京農大の学長や教員を含む)が牽引した国策によって、多くの若者が死へと追いこまれたのである。
私はその東京農大を卒業し、現在も奉職している。本を出したのはもちろん、母校を糾弾しようとしたのではなく、むしろ学生時代、キャンパス内にある慰霊碑の存在を知りつつ、ずっと無関心、無責任に素通りしていた自分自身を問い直すための作業であった。

国家や大学に息づく無責任体制
2002年、東京農大の新任教員として卒業生のインタビューを担当することになった私は、満州報国農場の生き残りの方々のお話を伺い、この事件が、決して遠い過去の出来事ではなく、国家や大学の中に今も脈々と息づいている無責任体制と通底していることに気付かされた。
そして、明治以降形作られてきた農学という学問自体に、農民や学生を軽視する構造的な欠陥があったのではないかと考えるようになった。こうして農大の歴代学長を含む、日本の近代農学の確立に貢献した学者たちの言動を一つひとつ検討し、これまで私自身が疑うことなく受け入れてきた農学という学問の枠組みを問い直すことに着手した。それは、自分自身をいったん解体して、また新たに立て直すような、かなりしんどい作業であった。
この作業をとりあえず形にすることができたのは、生還者の方々の一つひとつの証言に突き動かされたからである。例えば、本書には登場しなかったが、農大報国農場からの逃避行を引導した上級生の東海林仲之介さんは、晩年「自分の骨は墓に納めてくれるな」と家族に遺言している。多くの仲間たちが、満州で斃《たお》れたままになっているのに、自分だけが安穏と墓に納まるわけにはいかないというのが、東海林さんの信念であった。

「報国農場」は食糧増産のため、また開拓移民の拠点として、1943年より満州各地に約70カ所設立された。自治体や団体などが各農場に送り込んだ人員は計約4600人(終戦時)。大人たちは現地で軍に召集され、残ったのは13~18歳程度の若者(少年少女)がほとんどだった。
日本軍が現地人(満人)から奪った土地で食糧増産に取り組むも、多くは寒さや飢えで過酷な生活を強いられ、終戦時にはソ連軍や満人らの略奪にも遭って、計1000人以上が死亡、約650人が帰国できなかったといわれる。
①の「東京報国農場」(計約400ha)には、都下市町村より青年男女計64名が勤労奉仕隊として送り込まれた。朝倉康雅さんもその一人。②の「東京農大湖北報国農場」は東京農業大学によって設立され、拓殖科の学生が実習と称して送り込まれた。
生き残らされた者の使命
「生きている自分と、死ななければならなかった友とを分けたものは何だったのか?」
生還者たちが生涯かけて繰り返し自問自答してきた、この問いかけは、約20年前の地下鉄日比谷線事故で親しい友人を突然亡くした私自身にとっても共通の問いかけであった。生き残ったのは、現状分析が正確だったとか、予知能力に優れていたとか、体力があったとか、処世術に長けていたなどという、サバイバル能力とは無関係である。彼ではなく、私が死んでもよかったのだし、むしろ本当は私こそ死ぬべき存在だったのかもしれない。
しかし、彼ではなく、私が生き残らされたからには、私には、彼の分まで生き、このような悲劇が二度と起こらないように考え、行動する使命が課せられていると受け取るほかない。そのような意味では、私も、満州報国農場の悲劇の生き残りのひとりである。私自身、時代は違えど、東京農大の農業拓殖科に入学し、1年次の農業実習を経験したひとりなのだから。
このような「生き残らされた」という感覚は、あえて言わせていただけば、戦争のみならず、阪神大震災や東日本大震災を経験したすべての人に共通な感覚だといってもよいであろう。もちろん、生き残らされた私たちも、あと幾ばくか生きた後、やがて亡くなった友と同じようにこの世を去ることになる。だが、生き残らされたしばしの間、あの悲劇を最後にすべく、私たちは最善を尽くさなければならない。
教訓を次の世代に引き継ぐ
『農学と戦争 知られざる満洲報国農場』(足達太郎、小塩海平、藤原辰史著、岩波書店)。農文協「田舎の本屋さん」にて発売中
この本にも寄稿してくださった生還者の黒川泰三さんは、東京農大を卒業するに当たって編んだ『白樺』という手書きの回想録のあとがきに、「真珠貝はわが身の痛さに堪えずして真珠を輝かす」のフレーズを掲げている。あたかも阿古屋貝が体内に異物を注入され、痛みに耐えかねて流す涙が真珠となって結晶するように、満州報国農場における殉難の悲劇も、繰り返し掘り下げることによって珠玉の輝きを析出させることができるはずだという決意表明である。
約40年後、満州報国農場からの生還学生たちは、黒川さんの編集により『凍土の果てに 東京農業大学満州農場殉難者の記録』(記録刊行委員会、1984年)を刊行した。この本には、
①なぜ自分たちが終戦間際に満州へ送られなければならなかったのかに関する戦争指導者たちの責任
②満州での犠牲者は、東京農大の学生を含め、単なる戦争犠牲者ではなく、侵略者にほかならなかったのだという自らの責任
③あのとき満州で純粋な死を遂げた学友たちと、いま桎梏《しっこく》の世界に息づいている自分たちと、どちらが幸せというべきかを考えた時、その実体験から得た生命観を、果たして次代へ引き継ぐことができるのかという不安
について意を砕いたという心情が吐露されている。
私たちも、生還者たちと同時代を生きているものの責務として、志を受け継ぐだけでなく、さらに次の世代にも教訓を伝えていく使命がある。教員である私にとっては、東京農大の現役学生たちと志を共有することが、さしあたっての課題となるであろう。
農業には本来、希望を抱かせる力がある
私たちは今回、農学という学問が担った負の歴史について掘り起こしを試みた。しかし、次回はぜひ農学という学問が指し示す希望について、語ってみたいと思う。
東日本大震災のしばらく後より、東京農大のOBと学生たちが、「農大復耕支援隊」を立ち上げて被災地でボランティア活動を展開している。彼らが福島県で花の球根を植えた時、あるおばあさんがこう言ったそうだ。「家も家族もなくして、生きる気力も失せたけれども、この花が咲くまでは生きてみたい……」。
農業には、絶望の中にあっても希望を抱かせる力がある。農学者にはそのようなヴィジョンを描く責務があるのではないだろうか。
私はマルチン・ルターが言ったとされる「たとえ明日世界が終わろうとも、私は今日タネを播く」という言葉が好きだ。明日世界が終わるなら、タネなど播いてもむなしいだけではないかと思われるかもしれない。しかし、人は食物によってのみ生きるのではなく、希望によってこそ生きる存在である。
涙をもってタネを播くのは、収穫の喜びを先取りして生きることができるからにほかならない。苦難の中にあってこそ、その希望は輝きを増してくるのではないだろうか。
(東京農業大学)
*月刊『現代農業』2019年9月号(原題:農学と戦争、そして農業の希望)より。情報は掲載時のものです。