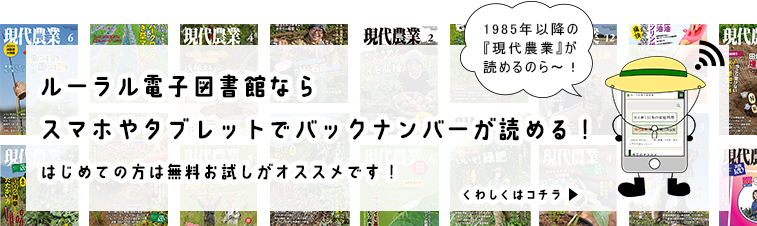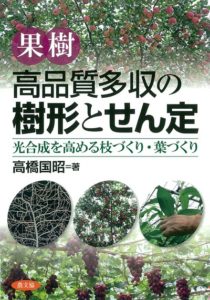山梨県南アルプス市・深澤 渉さん


ラクしていいものをとる
左右2本の主枝がYの字に伸びて、亜主枝が真横に何本も伸びる。魚の骨のようにシンプルな形で、素人目にも作業性のよさが想像できる。
「管理作業は高所作業車を使ってます。受粉、摘果、摘心、収穫と、亜主枝に沿って真横にずらしながら作業していくだけ。うんとラクですよ」
山梨県南アルプス市の深澤渉さん(80歳)が、試行錯誤のうえにたどりついたスモモの樹形だ。深澤さんといえば、2007年3月号や2008年7月号でわい化リンゴのトレリスを活用したスモモやナシの「垣根仕立て」を紹介してくれて、大きな反響を呼んだ。現在は、その作業性のよさを引き継ぎつつ、トレリスなしで仕立てる「ふかさわ流 自然形Y字仕立て」に進化しているというのだ。

「親父から引き継いだときは、周りの農家と同じ開心自然形。10尺の脚立でも届かないような大木でした。樹のふところは暗くて太い枝が伸び、結果枝ははるか上のほう。脚立から落ちて背骨を圧迫骨折したこともありましたよ。

50、60代の頃は山梨の果樹園芸会などの役をやっていたんで、月の半分くらいは会合に出てました。あの頃は女房と2人で2町歩の観光農園を切り盛りしてたから、なんとかラクしていいものとりたい。そればっかり考えて、試行錯誤してきたんです」
こうしてたどりついたのが、現在の仕立て。脚立で収穫する観光農園のお客さんからも「あちこち向かなくていいから、とるのがラクだし、安全」と好評だ。
樹形も家庭も「オヤジを立てよ」
深澤さんは骨格枝の仕立て方を、こんなふうに説明する。
「主幹の延長が第1主枝、その脇から1、2年遅れて伸ばしたのが第2主枝。第1と第2は差をつけないといけません。家庭でいうとオヤジと女房。女房が出過ぎてオヤジを負かしてしまうと樹はおしまい」
つまり、第1主枝の先端が力を損なわないように樹勢を保ち、つねに「オヤジを立てる」のが大事だという。
また、「主枝から出る徒長枝は不良の『悪たれ息子』」ともいう。威勢ばかりよくて働きが悪い(実がつかない)からだ。これを勢いづかせると、一家離散の憂き目にあう(樹勢バランスが崩れてしまう)。だから、「悪たれは指導しましょう」と摘心(後述)や夏季せん定で短く切り戻す。
一方、亜主枝として家族を支える「孝行息子」は、主枝の真横から少し下の位置から出た枝たちだ。これを主枝に対して90度の角度(地面と水平)に誘引する。この角度が鋭角になると「強くなりすぎて親の邪魔をする」。竹で水平に誘引することで家族のバランスが整うし、作業者にとっても働きやすい樹形となるわけだ。


ブドウの摘心と同じ
この樹形を維持するために必要なのが摘心である。スモモの開花はモモより10日ほど早い3月20日頃。花が咲いたあとに新梢が伸び出し、5月中旬(摘果作業の前後)には10芽くらいに伸びる。そこで・・・
この続きは2021年11月号または「ルーラル電子図書館」でご覧ください
*月刊『現代農業』2021年11月号(原題:ふかさわ流 スモモ自然形Y字仕立て 摘心で結果枝を小枝に)より。情報は掲載時のものです。
今月号のイチオシ記事
2021年11月号の試し読み
今月号のオススメ動画
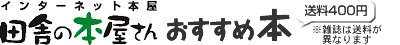
基礎からわかる おいしいモモ栽培
富田晃 著
施肥、整枝剪定の「樹勢管理」と、摘蕾・摘花/果の「着果調節」を軸に、安定高収のための基礎をていねいに解説。味の不揃い、待ったなしの軽労化対策など現場の課題に、長年の研究・指導の経験から答える。
果樹 高品質多収の樹形とせん定
高橋国昭 著
ビックリするような収量と品質をあげるには、光合成生産(物質生産)の量を増やし、それをいかに多く果実に分配するかが勝負。それをベースに高品質多収栽培の理論を確立し、生育目標、樹形とせん定、栽培法を解説。